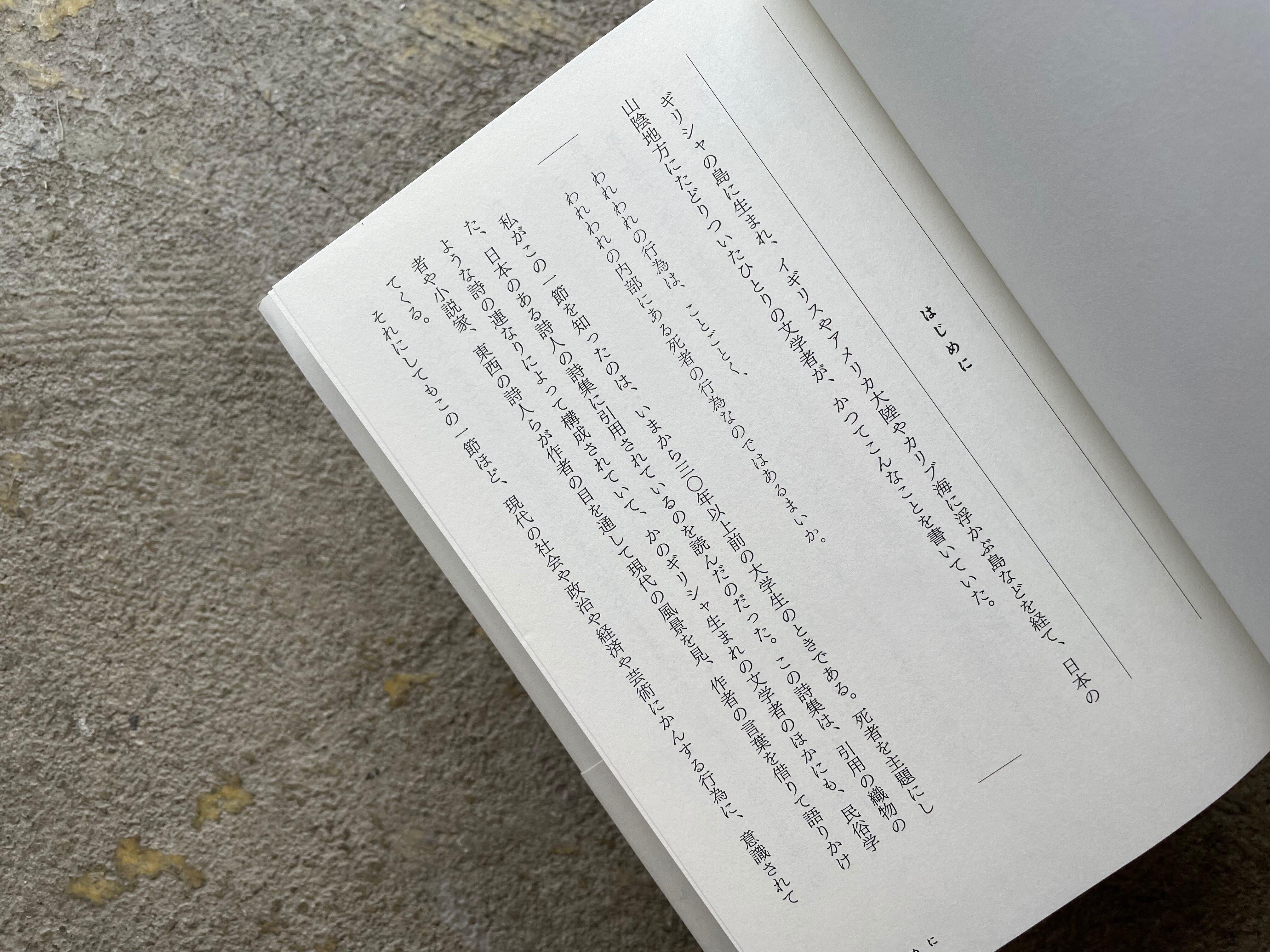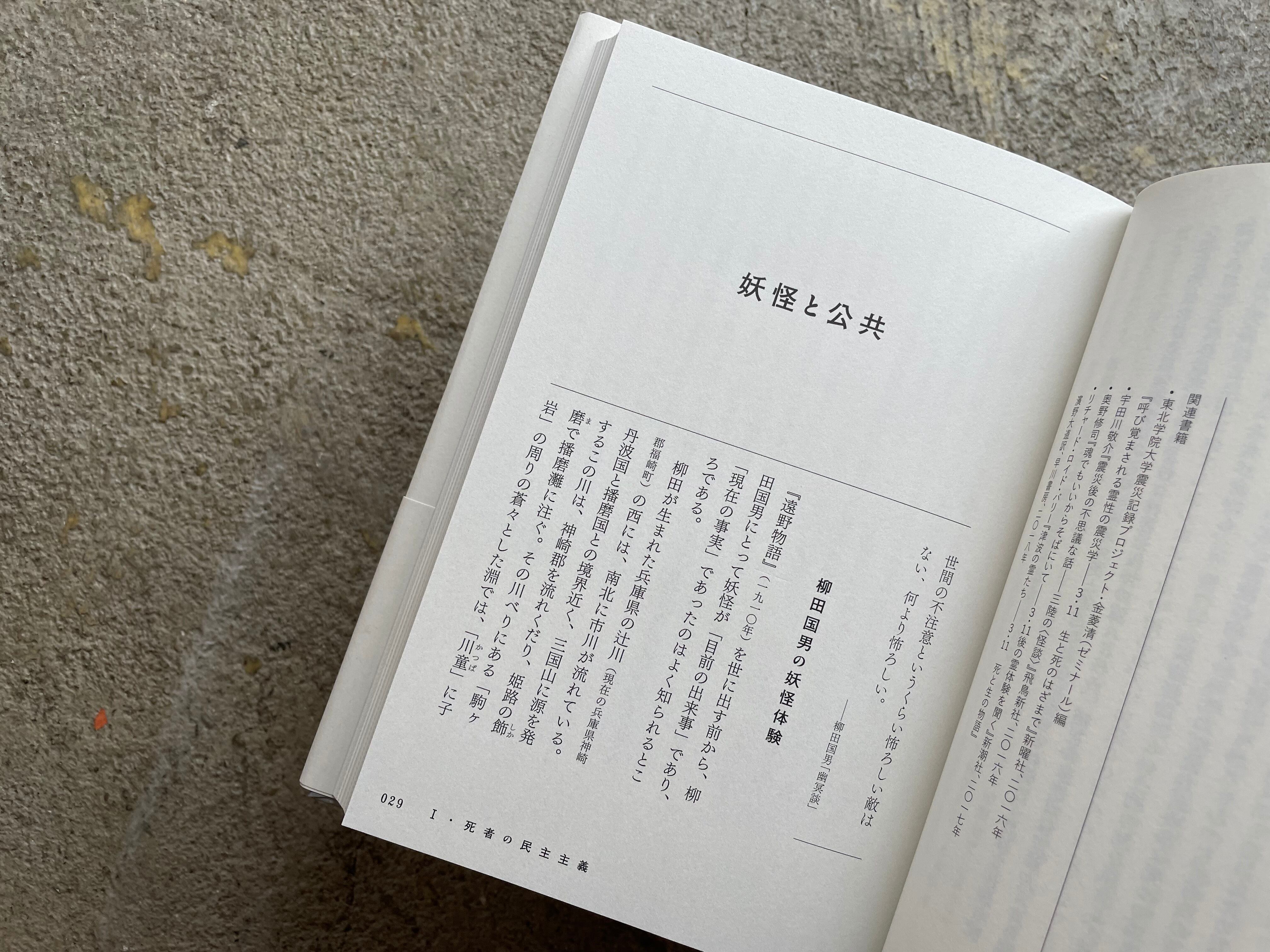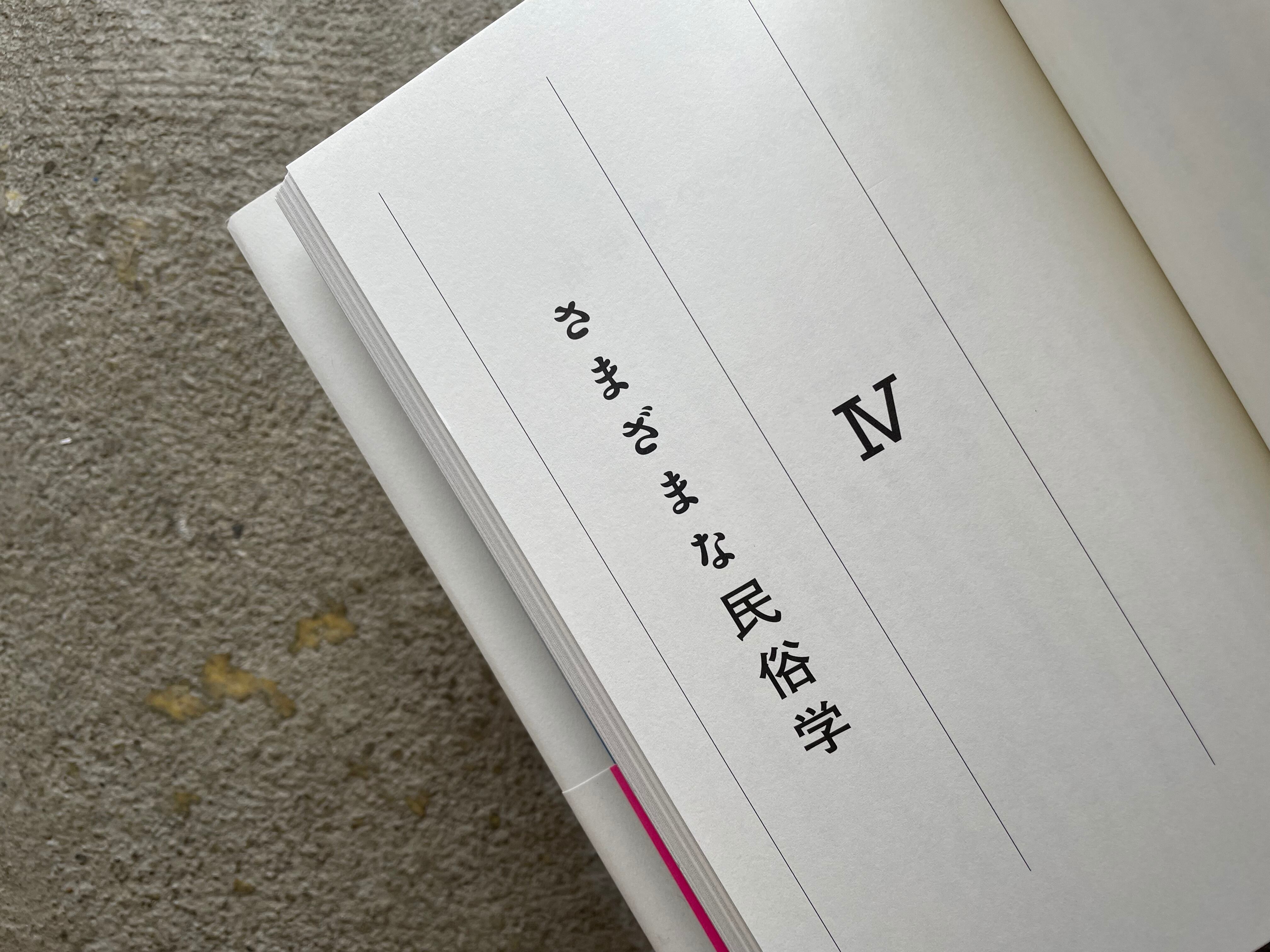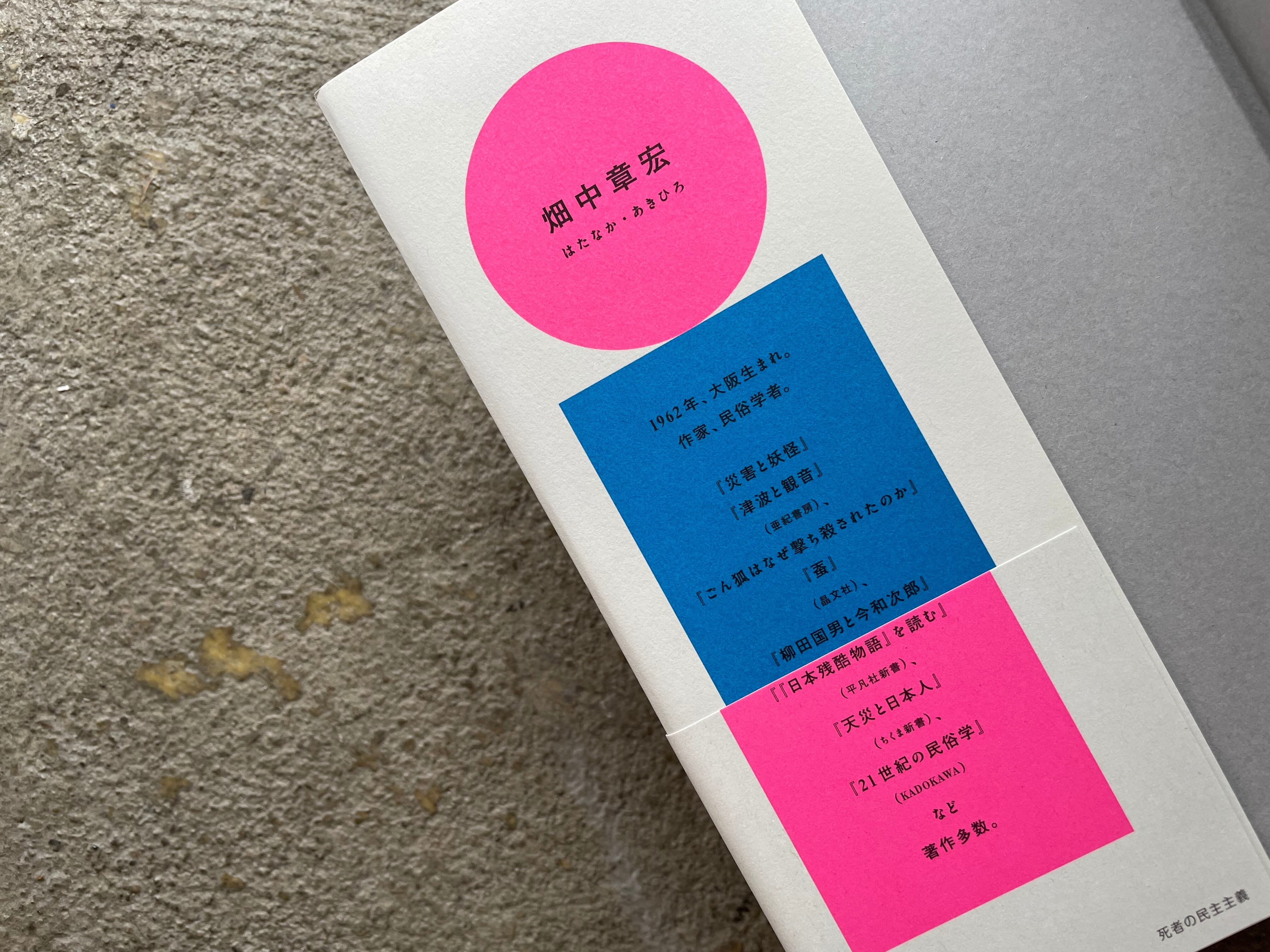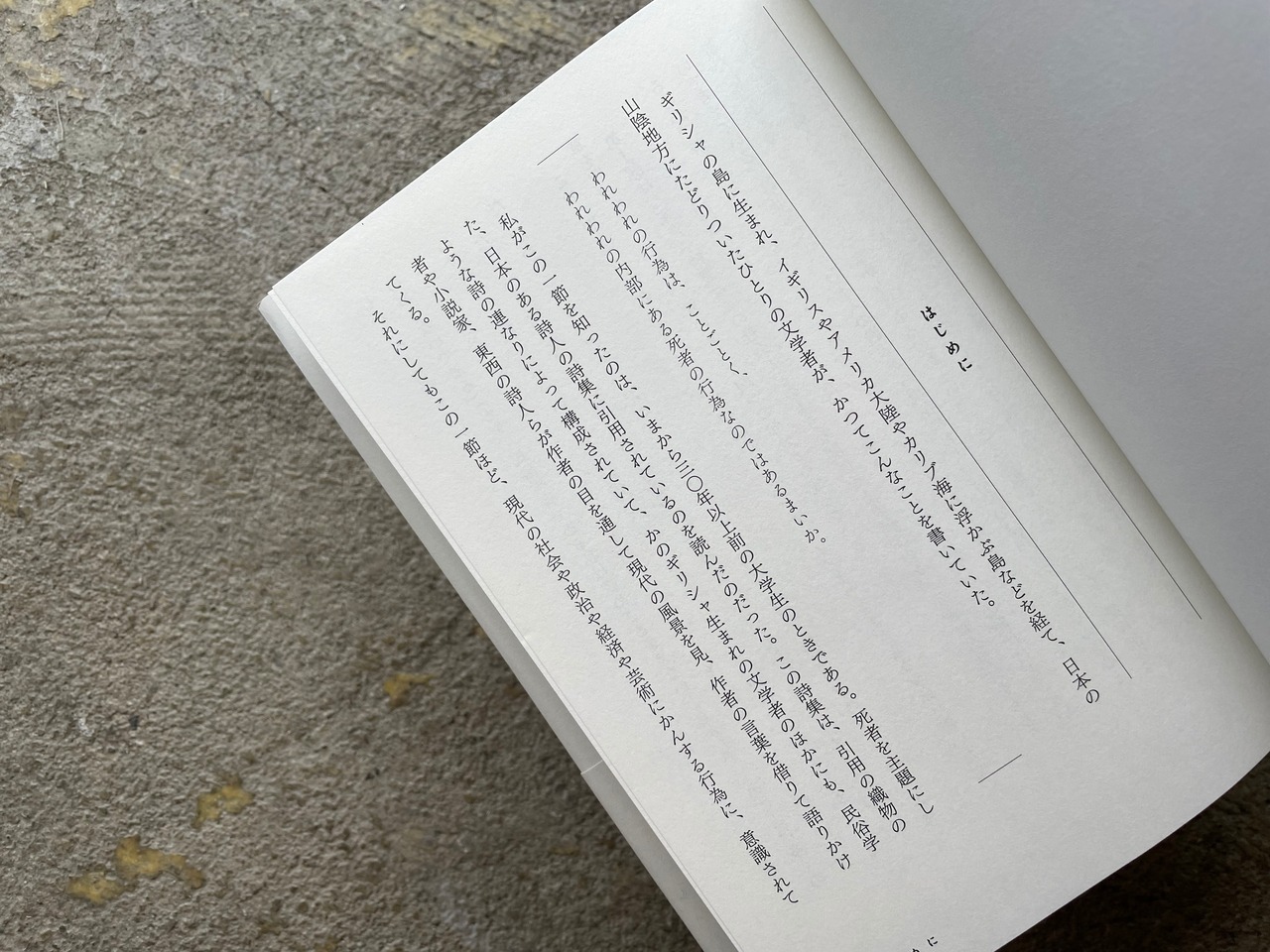
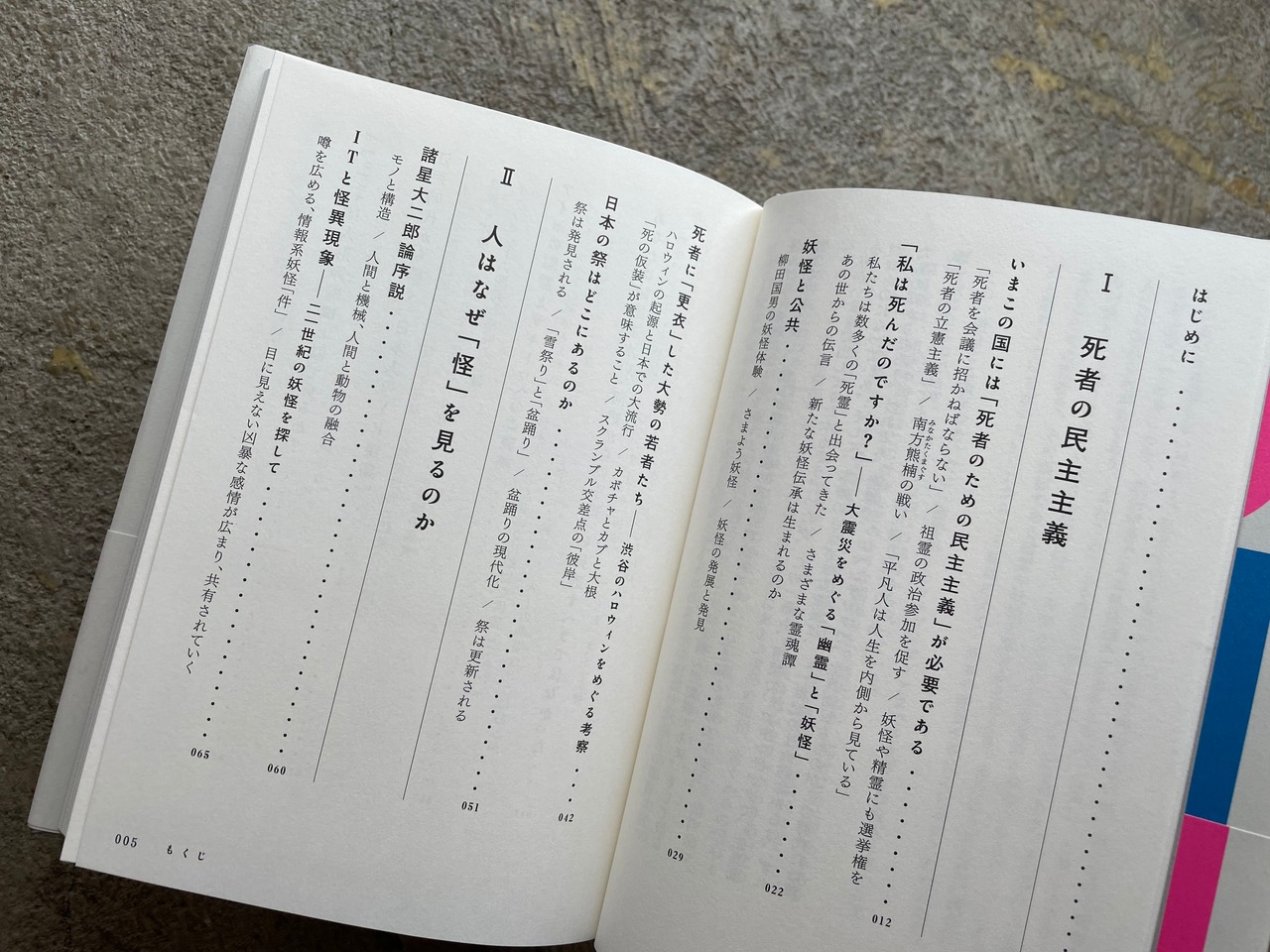





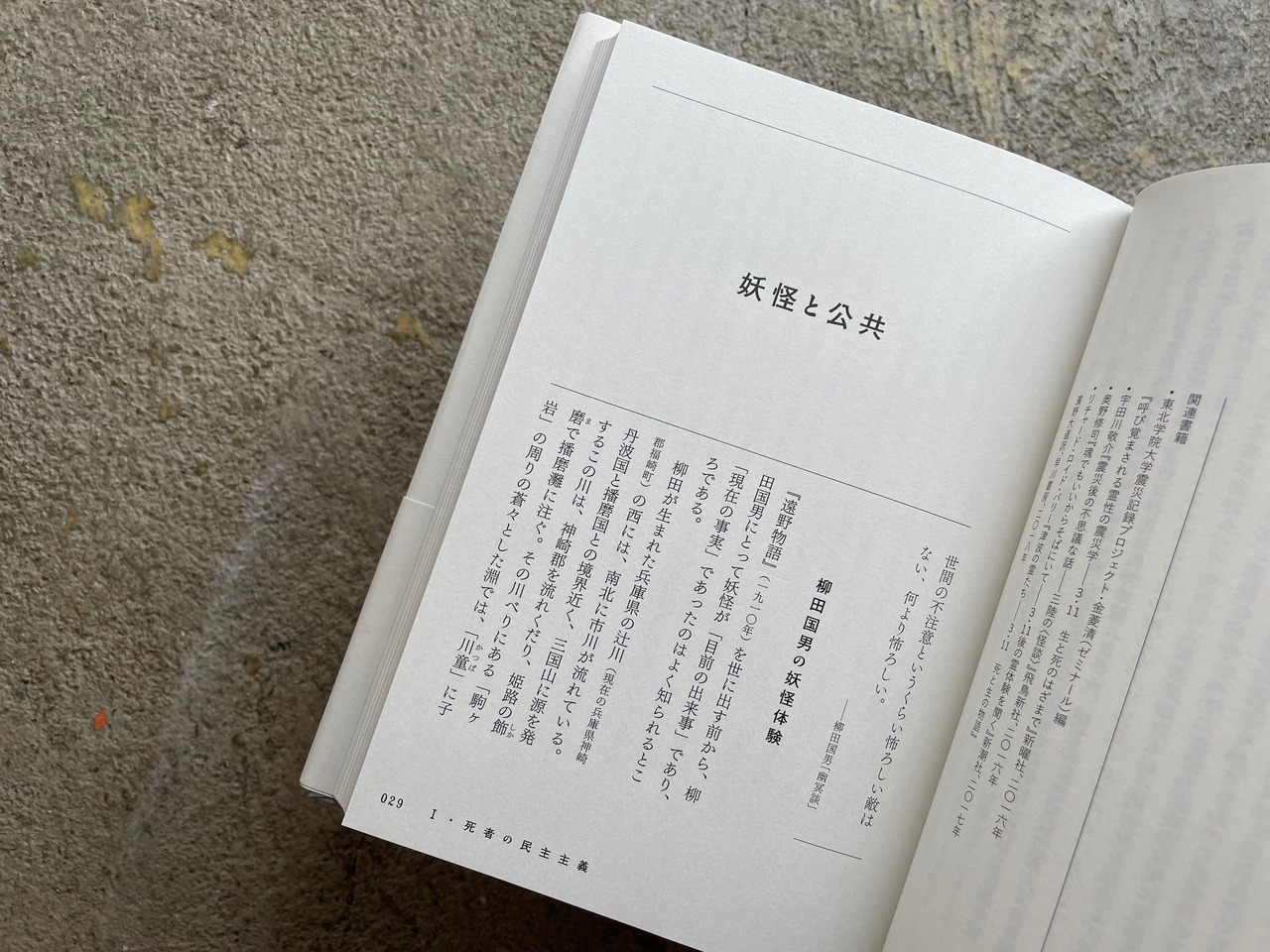




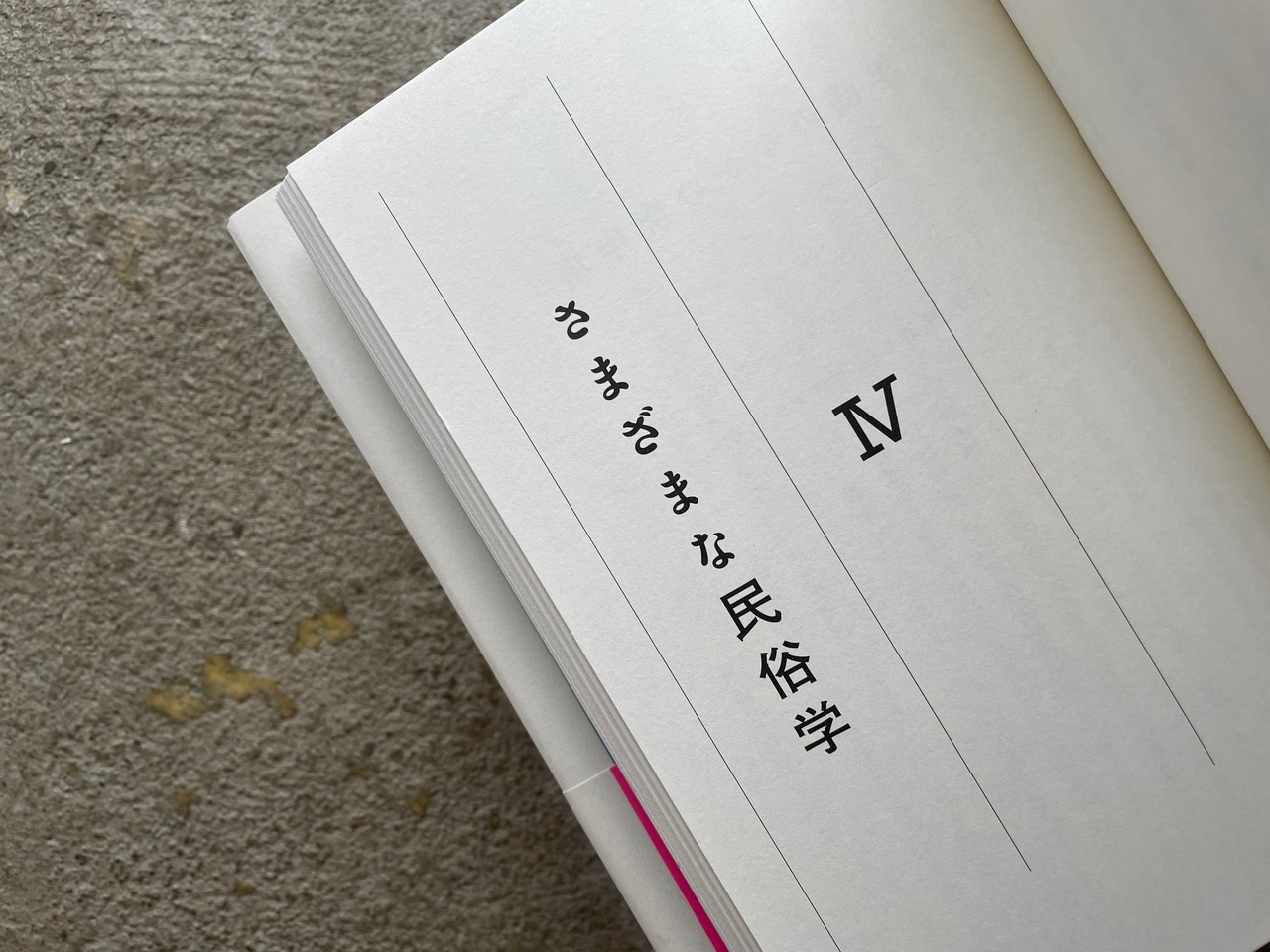



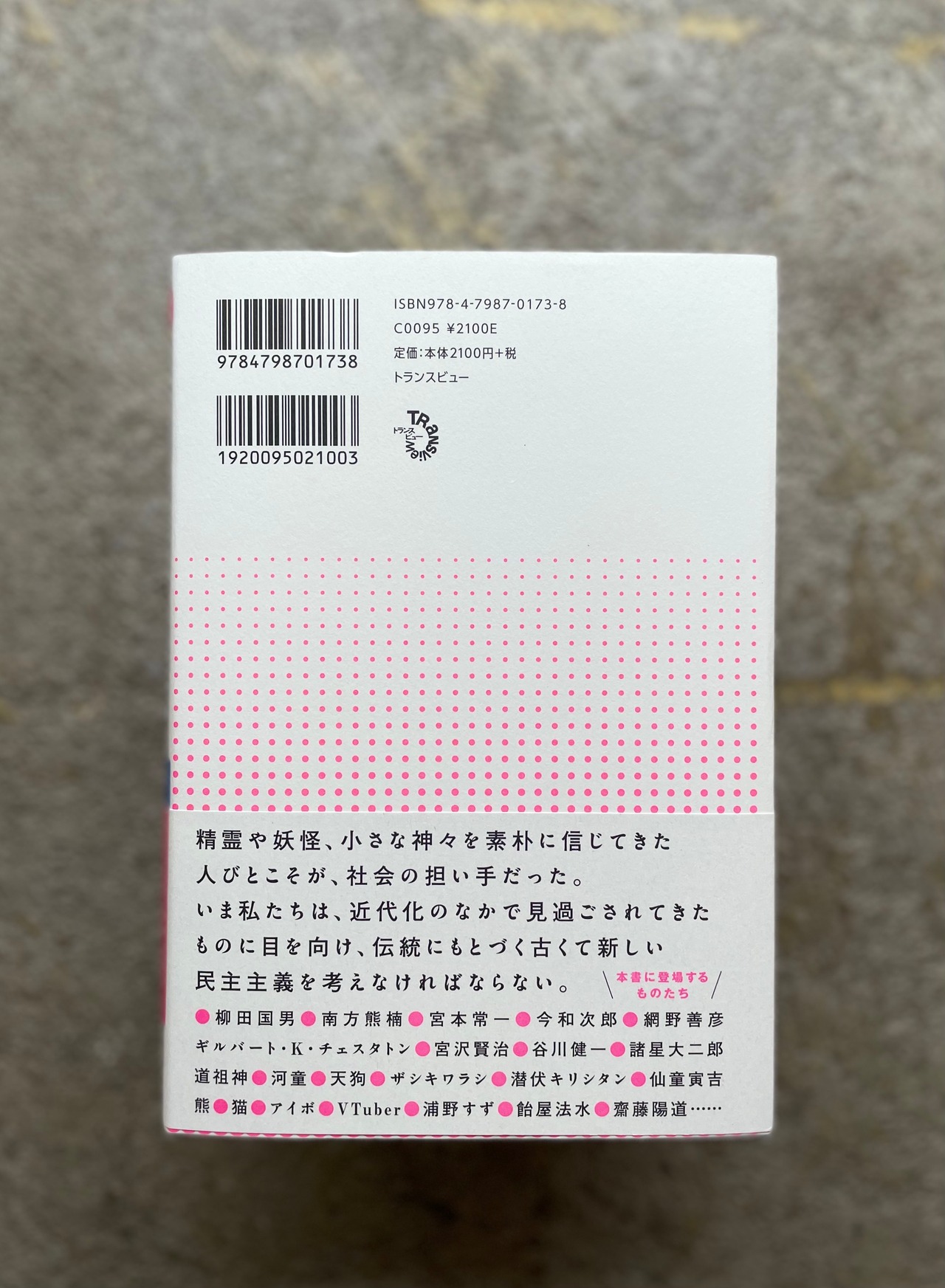
死者の民主主義
¥2,310 税込
SOLD OUT
別途送料がかかります。送料を確認する
『死者の民主主義』
畑中章宏
四六判
272ページ ハードカバー
人ならざるものたちの声を聴け
20世紀初めのほぼ同じ時期に、イギリス人作家チェスタトンと、当時はまだ官僚だった民俗学者の柳田国男は、ほぼ同じことを主張した。それが「死者の民主主義」である。
その意味するところは、世の中のあり方を決める選挙への投票権を生きている者だけが独占するべきではない、すなわち「死者にも選挙権を与えよ」ということである。
精霊や妖怪、小さな神々といったものは、単なる迷信にすぎないのだろうか。
それらを素朴に信じてきた人びとこそが、社会の担い手だったのではなかったか。
いま私たちは、近代化のなかで見過ごされてきたものに目を向け、伝統にもとづく古くて新しい民主主義を考えなければならない。
死者、妖怪、幽霊、動物、神、そしてAI……
人は「見えない世界」とどのようにつながってきたのか。
古今の現象を民俗学の視点で読み解く論考集。
〔本書に登場するものたち〕
柳田国男、南方熊楠、宮本常一、今和次郎、ギルバート・K・チェスタトン、網野善彦、宮沢賢治、谷川健一、諸星大二郎、道祖神、河童、天狗、ザシキワラシ、潜伏キリシタン、仙童寅吉、熊、猫、アイボ、VTuber、浦野すず、飴屋法水、齋藤陽道……
目次
Ⅰ 死者の民主主義
・いまこの国には「死者のための民主主義」が必要である
「死者を会議に招かねばならない」/ 祖霊の政治参加を促す / 妖怪や精霊にも選挙権を /「死者の立憲主義」/ 南方熊楠の戦い /「平凡人は人生を内側から見ている」
・「私は死んだのですか?」――大震災をめぐる「幽霊」と「妖怪」
私たちは数多くの「死霊」と出会ってきた / さまざまな霊魂譚 / あの世からの伝言 / 新たな妖怪伝承は生まれるのか
・妖怪と公共
柳田国男の妖怪体験 / さまよう妖怪 / 妖怪の発展と発見
・死者に「更衣」した大勢の若者たち――渋谷のハロウィンをめぐる考察
ハロウィンの起源と日本での大流行 / カボチャとカブと大根 /「死の仮装」が意味すること / スクランブル交差点の「彼岸」
・日本の祭はどこにあるのか
祭は発見される /「雪祭り」と「盆踊り」/ 盆踊りの現代化 / 祭は更新される
Ⅱ 人はなぜ「怪」を見るのか
・諸星大二郎論序説
モノと構造 / 人間と機械、人間と動物の融合
・ITと怪異現象――二一世紀の妖怪を探して
噂を広める、情報系妖怪「件」/ 目に見えない凶暴な感情が広まり、共有されていく / 人と人をつなぐ、目に見えない綱「キズナ」。
・VTuberは人形浄瑠璃と似ているか?
ぎこちない動きが心を揺さぶる / 社会との絶妙なバランス
・江戸時代から続く「日本人のVR羨望」
ツイッターから話題になった江戸の奇談 / 超常世界と超能力への関心 / 異界を体験し、超能力を身につけた少年 / 宇宙体験の真実 / テクノロジーの開発と感覚の拡張
・アイボの慰霊とザギトワへのご褒美
ペットロボットの献体とお葬式 / 日本人はどんなふうに動物を供養してきたか / アリーナ・ザギトワと日本の忠犬 / 犬を神に祀る神社 / AIの墓場はどこにあるか
・あなたは飴屋法水の『何処からの手紙』を見逃すべきではなかった
郵便局から届いた「物語」/ 語り出す「木」や「神様」/「いとおごそか」な神 / 無数のなかの、わずかのひとつ / ニンゲンがつくった神様
・「まれびと」としての写真家――齋藤陽道展「なにものか」
・『この世界の片隅に』は妖怪映画である
方言とカタストロフ /「かまどの煙」が意味するもの / 広島は「死んだ人のゆくところ」/ 原作に活かされていた「考現学」
Ⅲ 日本人と信仰
・縄文と民俗の交差点――八ヶ岳山麓の「辻」をめぐって
南大塩の辻 / 山寺の辻 / 御座石の辻 / 米沢の辻
・熊を神に祀る風習
クマの神籬 / クマの民俗 / クマの祭祀 / クマの童話 / クマの置きもの
・窓いっぱいの猫の顔
・移住漁民と水神信仰
摂津国佃村漁民の移住 / さまよう「水神」/ 波除様の魚介供養碑 / 佃煮と佃門徒 /「つきじ獅子祭」の合同渡御
・「休日増」を勝ちとった江戸時代の若者たち
日本人の長時間労働と勤勉性 / 沸きおこった「遊び日」の要求 / 若者たちが獲得した休日の実態 / オンとオフの絶妙な切り替え
・『沈黙』のキリシタンは、何を拝んでいたのか?
「潜伏キリシタン」と「カクレキリシタン」/ カトリックとは相いれない信仰 /「キリシタン神社」とは何か / 日本人の信仰の「縮図」
・戦後日本「初詣」史――クルマの普及と交通安全祈願
近代初詣の誕生 /「成田山」の戦中と戦後 / 自動車祈祷殿の流行 / 交通安全と初詣の未来
・大阪万博と知られざる聖地
五五年越しの開催 / 千里丘陵という地勢 / ヘリコプターからお祓いをした地鎮祭 /「太陽の塔」と千手観音
・日本人にとって「結び」とは何か――正月飾りに秘められた驚きの科学
日本古来の「結び」文化 / 家紋や社紋と結びの多様性 /「あみだくじ」を幾何学から捉える / 日常に遍在する「結び」の数々
Ⅳ さまざまな民俗学
・手帳のなかの庚申塔――宮沢賢治と災害フォークロア
賢治と地震と地震 / ザシキワラシと白髭水 / 七庚申と五庚申
・「青」のフォークロア――谷川健一をめぐる風景
若狭の「青」/ 志摩の「青」/ 対馬の「青」/「青」の現在
・写真と民俗学者たち
「民俗と写真」座談会 / 土門拳と柳田国男 / 柳田国男の写真 / 写真と柳田の弟子たち
・東北に向けた考現学のまなざし――今和次郎と今純三
・「百姓」のフォークロア――網野善彦の歴史学と「塩・柿・蚕」
百姓再考 / 塩 / 柿 / 蚕
畑中章宏(ハタナカアキヒロ)
1962年、大阪生まれ。作家、民俗学者。『災害と妖怪』『津波と観音』(亜紀書房)、『ごん狐はなぜ撃ち殺されたのか』『蚕』(晶文社)、『柳田国男と今和次郎』『『日本残酷物語』を読む』(平凡社新書)、『天災と日本人』(ちくま新書)、『21世紀の民俗学』(KADOKAWA)など著作多数。
-
レビュー
(1243)
-
送料・配送方法について
-
お支払い方法について
¥2,310 税込
SOLD OUT